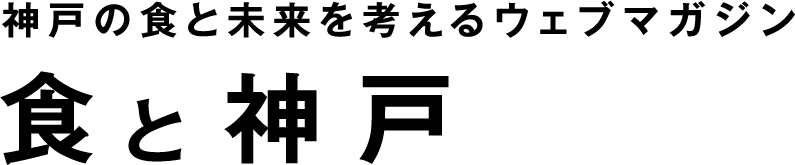瀬戸内の食文化をめぐるレポート vol.7 和歌山 前編(ひろげる)
かつては、西日本の交易の中心だった瀬戸内。そんな瀬戸内エリアには、新たな食にまつわる活動や動きが生まれつつある。今回の取材では、瀬戸内の各県を巡り、「つくる人」「ひろげる人」という視点から、各地のプレイヤーの取組みを発信し、食文化を発展させていくヒントやきっかけを見つけ、ネットワークを構築していく。
今回は和歌山県のプレイヤーに会いにいく。徳島県美馬市で建築設計の仕事を営む高橋さん、そして兵庫県神戸市でカメラマンをしている岩本さんと車を走らせ、右手に大阪湾を臨みながら和歌山県に入っていく。
家業を継ぐ中で見えてきた、自分の役割

下津というインターチェンジを降りて、西へ。山を見渡せばみかんの木々が広がる集合場所は、なぜか農協のとある施設だった。
「遊休施設を活用してほしいということで、この場所で『KAMOGO』というカフェを始めました。釣り人くらいしか来る目的がなかったこの町のカフェに、年間2万人のお客さんが来てくれているんですよ。」
そんな話から教えてくれたのが、海南市下津町を中心に様々な活動を展開する『FROM FARM』の大谷幸司さん。ひろげる人としてのお話を伺う。大谷さんはここ下津町の出身で、みかんや花の農家をしている一家の下で育った。田舎や農家であることが嫌で、就職を期に愛知県に出たものの、20代後半の時に父親が倒れ、予期せずUターンをすることに。
「設備投資の借金もあったので、7年間ぐらいは必死にただただ農業をしていました。ようやく返済も進み、少し心にゆとりが出てきた時に、ふと地域の産業のことや課題に目が向くようになってきました。今やっていることが、本当に自分のやりたいことなのか。この地域でできることはどんなことなのだろうか。そういうことを考えるようになりましたね。」
様々な取り組みの中で知る、地域が本当に困っていること

そういった内なる意識から、自分が畑に出るというスタイルを少しずつ変えていく。
「和歌山には『ぶどう山椒』というブランドがあるのを知り、実際食べてみたらそれがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。それから和歌山はフルーツ王国でもあるので、僕が生産するしないということよりも、産地のものを生かしてどう発信できるかとかということに取り組んでみることにしました。」
大谷さんは、ぶどう山椒を活かした山椒の塩や、ドライフルーツを活用したグラノーラなどを開発し販売を始める。また、カフェをオープンすることで、地域の農作物の魅力を発信していった。若い世代を中心に下津町に人が訪れるようになり、手応えも出てきた。しかし大谷さんは、ある現実に直面する。
「自分としては、農業とか地場産業を盛り上げたい、面白くしたいという気持ちでやっているんですけど、地元の農家さんはあまり求めていないっていうのを感じて。加工品にするために僕が買い取れる量も知れていて、多少買取価格が高かったとしても、農家さんからしたら助かってるということにはならないんです。自己満足にしかなってないんじゃって思ったときに考え直して、農家さんが一番困ってることは、やっぱり後継者不足なんですよね。もうみんな60代後半、70代。このままでは産地が終わると。」
かつて、みかんの多忙な収穫時期は、親戚や近隣のお手伝いさんによって賄われてきた。しかし、そうした人々も高齢化のため引退し、収穫できるものがあるのに収穫し切れないということが深刻化し始めていた。そこで大谷さんは、『みかん援農』というコーディネート機関を立ち上げ、田舎暮らしに興味のある若者たちが、季節労働としてみかん農家に入り込む流れが生まれた。
「お互いすごく求められましたね。農家さんは、農業に興味ある若者が前向きな気持ちで来てくれるから、助かるし嬉しい。若者にとっては、山に登ってみかんを収穫するっていう作業自体がもうアトラクションで、新鮮で楽しいだけでなく、農家さんも喜んでくれる。正解が分からない世の中で、繋がりや経験に価値を置くっていうことに変わってきているような気がします。」

photo by Kouji Ootani
自分がハブになり、エリアとしての魅力を高めていく

地元の特産品を活かした商品を作り、カフェを入り口に町を知ってもらい、援農という形で人々が町に入り込んでいく。今後、大谷さんが取り組みたいことを聞いてみる。
「就農に興味を持つ子も出てきたりするんですけど、その次に繋がるのは結構ハードルが高いので、就農しやすい環境だったり引き継げるような仕組みを模索したいです。また、私たちのカフェがハブになって、エリアとして、新しいお店や宿を始めるような仲間が増えていったら。私が誰よりも良い生産者で、魅力的な生産物を作るってことよりも、こうした動きをした方が私としての意義があるというか、そういう役割を担っていきたいですね。」
自分が生まれ育った町全体を、点ではなくエリアとして魅力を高めていく。そんな壮大な話も、大谷さんなら1つずつ仲間と形にしていきそうだ。最後に、大谷さんは『食文化』という言葉をどう捉えますか?
「今って、当たり前に食べられる時代じゃないですか、当たり前にあるものって、興味を持たれないですよね。でも例えば、あの山にある段々畑は、まだ車も何もない時代に、人々が開墾して、石段を全部積み上げて作ってるんですよね。田んぼも同じで、家の場所よりも、田んぼの場所を大事にしたわけです。放棄地は山に戻り、田んぼは宅地になり、失われたものはもう戻ってこない。やっぱり時間をかけて現状を整え直していって、初めて繋がることだと思っています。文化というかその価値に気付いて、自分なりの形で何かを生み育てていく人を増やしていきたいですね。」
強い危機感の中にも、人を包み込むような柔らかさを持つ大谷さん。大谷さんを中心に、新しい人と人との関わり方や、文化のあり方が生まれていくような気がした。
●おまけコラム「和歌山県の郷土料理」
今回の取材は、「各県の郷土料理を食べる」というテーマをいただいている。瀬戸内海に面する四国三県では麺の勢力が強く、その追い風を受ける形で和歌山県でもこちらを選ばせていただいた。

和歌山ラーメンだ。いやちょっと待て。またラーメンか、自分たちが食べたいもの食べてるだけだろ。そんな批判を受けそうであるが、ここには意図があることを聞いていただきたい。瀬戸内の新しい交流のあり方を探る今回の企画であるが、かつてから、和歌山と徳島には船の行き来があったようだ。ご当地ラーメンといえど様々な系譜があるので一概には言えないものの、和歌山と徳島の醤油をベースとしたラーメンは比較的近しいものがある。かつての交流の中で、醤油発祥の地と呼ばれる和歌山の醤油ベースのラーメンが徳島に伝わり、徳島で進化したラーメンの影響を和歌山がまた取り入れ、相互に発展したのかもしれない。そんな至極勝手な想像をしながら食べるラーメンは、やっぱり美味しい。『早すし』というお寿司と共に食べるのが和歌山ラーメン独特のスタイルであり、ラーメンをすすりながら頬張ると、「あーー和歌山来たなぁ。」と全身で感じるこの喜び。いや結局、食べたいものを食べてるだけのような気もしてきた。
後編に続く。
記事では書ききれなかったことなど、取材時の様子を動画で公開しています。
より詳しくご覧になりたい方はこちらから。
文:鶴巻耕介
写真:岩本順平