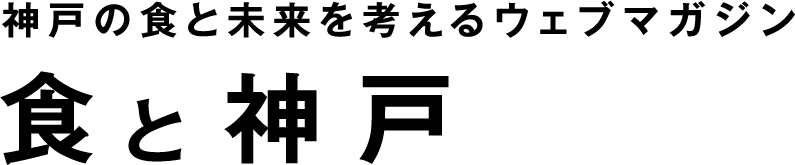瀬戸内の食文化をめぐるレポート vol.9 岡山 前編(つくる)
かつては、西日本の交易の中心だった瀬戸内。そんな瀬戸内エリアには、新たな食にまつわる活動や動きが生まれつつある。今回の取材では、瀬戸内の各県を巡り、「つくる人」「ひろげる人」という視点から、各地のプレイヤーの取組みを発信し、食文化を発展させていくヒントやきっかけを見つけ、ネットワークを構築していく。
今回は岡山県のプレイヤーに会いにいく。徳島県美馬市で建築設計の仕事を営む高橋さん、そして兵庫県神戸市でカメラマンをしている岩本さんと車を走らせ、岡山市中心部から20分もかからずに、北区牟佐という農村地域に辿り着く。
一杯の味噌汁が、自分の進む道を決めた

集合場所に近づくにつれ、ビニールハウスには黄色い数字が貼られ、黄色い看板が立ち並ぶ。倉庫の前にある農機具の持ち手もなぜか黄色に塗られている。そして現れたのが、メガネもつなぎ服もマスクも黄色一色、ARCH FARM代表の植田輝義さんだ。今回は、つくる人としてお話を伺う。
「お付き合いしていた彼女の家に初めて遊びに行ったときに、黄ニラっていう野菜を目の当たりにして、感動的で綺麗な光景だったんです。そして、その黄ニラを使ったお味噌汁をお母さんが出してくれて、その一杯の味噌汁があまりにも美味しかったんですよね。」

photo by Teruyoshi Ueda
当時のことを教えてくれる植田さん自身は、兵庫県西部にある揖保郡太子町の出身。24歳の時に、黄ニラ農家の婿養子として、岡山市北区牟佐に飛び込んできた。黄ニラは、明治初頭から栽培が確認され、岡山県が発祥と言われている作物で、太陽の光をカットすることで黄色になって育つのだという。そして植田さんのもう一つの武器は、パクチーだ。
「今から22年前、就農した翌年に、東京市場の関係者からパクチーを作ってみないかと言われたのがきっかけです。当時はまだどんな野菜かも分からないような時代でしたし、インターネットも充分に普及していなかったので、とりあえず見よう見まねで種だけいただいてやり始めました。そこからお義父さんと棲み分けしながら、私の方はパクチーにも力を入れていきました。」
現在は会社を立ち上げ、約3.5haの農地を、従業員とアルバイト合わせて5名で運営する規模まで拡大している。
大使を名乗り、異業種と農業を掛け合わせていく

植田さんは、自身で『黄ニラ大使』『岡パク(岡山パクチー)大使』を名乗り普及活動もしている。あらゆるものが黄色で統一されているのは、こうした背景があったからだ。きっかけは何だったのだろうか。
「不思議だったんですよね。農家さんたちは声高らかに『うちらの黄ニラは日本一だ。』みたいに言うんですけど、一歩外に出て一般の方と話したら、みんな知らないんです。これで日本一ってどうなの?みたいに思って、まずは地元で普及をさせたいなと。あと私は太子町という名前の場所が故郷なので、ちょっとダジャレをかけて、新しい故郷の黄ニラと、自分の古い故郷の太子町を掛け合わせて、『黄ニラ大使』と自分で命名して活動を始めました。」
各メディアに黄ニラ大使始めましたとFAXを送り、飲食店にはアポなしで飛び込んだ。公民館や神社で行われるような小さな市やマルシェにも黄ニラのことを伝えるために通った。そうした地道な活動が徐々にメディアに知れ渡るようになり、気付けば地域のシェア率が大幅に上がり、テレビやラジオで数多く紹介され、給食にも使われるようになっていった。そういった中で、植田さんはあることに気付いていく。
「異業種といいますか、違う業種や違う人たちとの繋がりというのは本当に大事だなと、23年間農業をやってきて感じています。同じ仲間で集まってというのは発展しない気がしていて。だからこそ、厳しく言ってくれる人だったり、違う角度で意見を言ってくれる人だったり、そういう人たちとコラボしてやっていく方がうまくいく確率も高いだろうなと思っています。」
黄色いつなぎ服の仲間を増やし、思い切り農業にチャレンジしてほしい

植田さんは、自身の体験を重ね、これからのことについて語る。
「僕の野菜や、岡山の野菜を選んでもらえるようにしていきたい。そこはもうずっと変わらないんです。やっぱり年々高齢化してきて、農地をどうにかしてという話も出てきています。そういったものを何とか活用しながら、農業を頑張りたい人に繋いであげたいですね。農業は、あらゆる面で新規参入のハードルが高く、設備投資も、販路を見つけるのも大変です。我々ARCH FARMの使えるものは全部使ってもらったらいいんですよ。夢は、ARCH FARMのグループを作って、黄色いつなぎ服のメンバーをどんどん増やしたい。まず岡山で100人増やしたいですね。」
植田さんは、自分を利用してくれたらいいと話す。自身も外から集落に入り、時代に合わせて変えていくべきこと、進化させていくべきことの議論がかみ合わず、悔し涙を流したこともあったという。そうした時に、お義母さんから『必ず、人が見てくれとるから頑張りなさい。』と言われ、植田さんはその言葉を胸にここまで走り続けてきた。そして後続のために、想いがあれば花開く場所を整えている。最後に、植田さんにとって、『食文化』という言葉をどう捉えますか?
「もう当たり前のことだなと思ってます。なくしちゃいけないものだと。特別なこともしてないし、特別な活動もしてないと思っています。食べ物だから絶対なくならないじゃんっていう奢りじゃなくて、消費者の方に食べてもらえる努力はどんどんやらないといけないんです。食べる選択肢を作るのが農家の仕事だと思っているので。ただ野菜作って、ただ米作って、ただ届けるっていうのはもう当たり前なんですよ。ここに、どう選んでいただけるかっていう選択を僕らが作れるかじゃないですかね。」
植田さんは、この問いに対して、一貫して生産者側からの目線だけを語っていた。消費者ではなく、まず自分たちからだ、そういった信念があらゆる行動に突き動かしていくのだろう。そしてインタビューを終え、「まあ、色々大変っすよ。」とやさしく笑う植田さんの表情もまた印象的で、人を惹き付ける魅力を感じる瞬間だった。
●おまけコラム「岡山県の郷土料理」
今回の取材は、「各県の郷土料理を食べる」というテーマをいただいている。今回は、『岡山ばら寿司』を選ばせていただいた。瀬戸内の各県の取材を巡る中で、寿司が郷土料理の一つになっている県がほとんどであり、瀬戸内の魚を美味しくいただく知恵は共通なのかもしれない。

運ばれてきたばら寿司は、目にも美しい。どれからいただくか迷うのも楽しく、岡山の海や山の幸を口いっぱいに感じながらあっという間に食べてしまった。このばら寿司、調べたところによると、江戸時代に「食膳は一汁一菜とする」という質素倹約が推奨される中、「ご飯の上に乗せても一菜は一菜」と庶民が反発し、ごはんの上に魚や野菜を乗せたことから始まったそう。―――このストリートカルチャーに胸が熱くなるではありませんか。話は少し変わるが、神戸の農村地域にも、農村歌舞伎舞台というものが現存している。当時農民は芝居の鑑賞や上演が禁じられていたそうだが、「これは収穫を祝う祭だ。」という名目で歌舞伎を楽しんでいたという。常にこうした現場からのうねりが文化になっていくのだ。私もよりよい社会にするために戦うぞ。そういったことを、食後の熱い茶をすすりながら穏やかに口を開いて妄想した。
後編に続く。
記事では書ききれなかったことなど、取材時の様子を動画で公開しています。
より詳しくご覧になりたい方はこちらから。
文:鶴巻耕介
写真:岩本順平