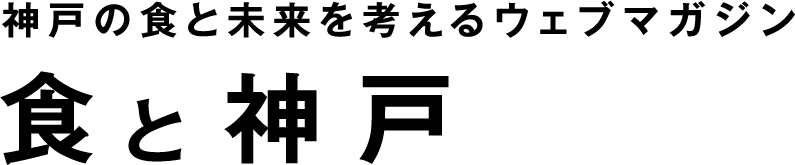これからの都市型農園01 農園の定義を広げよう
これからの都市型農園
新保奈穂美
01 農園の定義を広げよう ―「小屋」と農園の話―
上の写真は何だと思われるだろうか。別荘か、庭付き一戸建てか。実は、これは定義的には「農園/庭」である。
「農園」と聞くと土と農作物のみの光景を思い浮かべる方が多いだろう。そして、都市に残る農地は、しっかり耕作をして、建築物をおかないということを条件に、農地として認めてもらい税制優遇の適用を受けてきた。裏を返すと、それに従わないと、宅地並みの固定資産税や相続税がかかる。プロの農業を行う土地なら、このルールでよいと思う。しかし昨今の都市に登場している体験や交流を重視したさまざまな農園については、土と農作物のみある空間がそれに適したものなのだろうか。獲れたての作物を調理するためのちょっとしたキッチンや、交流・休憩のスペースも欲しいし、何より近年の夏には暑さから避難する小屋がないと命の危険すらある。
写真に示したウィーンのクラインガルテンでは、1990年代から大部分で通年居住が可能になり、「小屋」に代わって「住居」という、より大きな建築物も建てられるようになった。しかし、依然として都市計画上の位置づけは「緑地-クラインガルテン」であるし、通常の住宅よりはずっと広い庭を楽しめる。増える人口を市内に留めつつ、緑ゆたかな暮らしをしてもらおうという市の戦略だ。19世紀からの伝統を重んじる人は仰天してしまうだろうが、これも今時の都市型農園のあり方のひとつである。
越えてはいけない一線もあるだろう。しかし、変化も早いボーダレスのこの時代、もう少し柔軟に「農園」の枠もゆるめて、今の時代に合った都市型農園の姿を考え、認めてみてはどうだろうか。結果的にまちが活性化されるのであれば、これから人口減少で都市も生き残りを賭けた時代に、むしろ税収も増えるかもしれない。
《ウィーン気質》に学び、「あ、それもありなんだね」と、ゆるやかさを少し取り入れてみたいところである。
…ただ、農園と呼ぶには畑が少なくなりすぎている気もするが、一方でそれは「畑が一面にないと農園じゃない」と自分たちにかけすぎている縛りに気づかせてくれるものでもある。
新保奈穂美兵庫県立大学大学院 講師、淡路景観園芸学校 景観園芸専門員
東京大学で学部、修士、博士課程まで修了。2016年より2021年3月まで筑波大学生命環境系助教。ウィーン工科大学への留学、ニュージーランドのリンカーン大学での研究滞在など、海外でも数多くの都市型農園をリサーチしている。