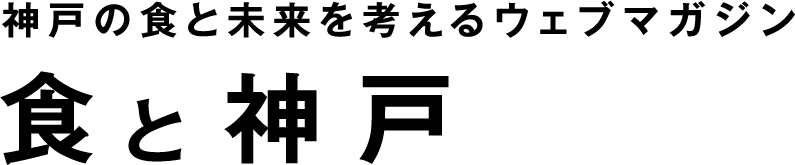瀬戸内の食文化をめぐるレポート vol.6 愛媛 後編(つくる)
瀬戸内各県で生まれ始めている、新たな食にまつわる活動や動きを展開している方々を訪ねていくレポート。今回は愛媛県の後編です。
(前編はこちら)
父親譲りの好奇心で、牧場を引継ぐ

前編でお話を伺った二宮さんに案内していただき到着したのは、同じく西予町内にある、ログハウスがシンボルの牧場『ゆうぼく』。美味しいランチをいただいた後、二代目の代表である岡崎晋也さんに、つくる人としてお話を伺った。1つ1つの質問に明瞭に答えていく頭の回転の早さと、時より発する好奇心の塊という両面が垣間見える。
「ログハウスを建てたのは父親です。すごいですよね。ある時、先代が築き上げてきたこの環境を使って、何ができるだろうっていう好奇心が芽生えてしまって。それでもう止められなくなってきちゃったんですよね。だから、父親がやってることを一生懸命守ってあげようとかって全然思ってないんです。」
先代である父親が脱サラをして始めた、牛を肥育する小さな牧場。しかし、育てた牛を牛肉として直売し、当時では珍しい無添加のハムやソーセージの加工も始め、ついには自分で建てたログハウスで飲食店までつくってしまう――。そうやって次から次に新しいことを仕掛けてきた父親を、横目で見ていた岡崎さん。2013年、そんな岡崎さんが20代後半でゆうぼくに入り、感じたことはなんだったのだろうか。
「店頭には無添加っていう言葉もないんですよね。我々は『はなが牛』というブランドでやっていますが、はなが牛っていう言葉を、社員ですら使っていない。価値のあることをしているのに、もったいないなと。そういった状況から、どうやってブランディングをして、価値を高めていこうかというのが最初の取り組みですね。ベースを整えていきました。」
この時代だからこそ、農業に原点回帰していく

ベースを整え、より発展させていく。そして、岡崎さんが2016年にゆうぼくを引き継いた後も、松山市内で飲食店を立ち上げたり、子牛を出産して自分たちで育てたりといった新たな取り組みが進んでいく。そんな中、一つのことが気になりはじめる。
「ソーセージの原材料は豚なのですが、このソーセージの原材料も育てているんですよねって言われることが結構あって。愛媛県産の豚肉を使い、無添加で加工していて尖った商品であるはずなのに、はなが牛と平行に並べるとちょっと弱くなってしまうことに違和感がありました。できるなら加工品の原材料も、自分たちで育ててますって言いたいなと。」
通常、牛は約2年、豚は約6か月という肥育期間であることや、餌や育て方の違いから、一緒に育てている牧場はほぼないそうだ。しかしゆうぼくでは、こうしたきっかけから豚を育てることにも挑戦し、様々な工夫を加えることで納得のいく豚肉を作ることができているという。結果的に、繁殖から販売まですべて行うことで、消費者への説明責任や、離農者問題等へのリスクヘッジといった強みにも波及していく。そんなゆうぼくの歩みを、岡崎さんはこのような言い回しで表現する。
「農業に原点回帰していくということです。普通は、農業から加工販売って下っていくじゃないですか。そうではなくて、Vの字のように、販売で得られたノウハウから逆に農業に戻るイメージです。農業に戻る先が豚だったり繁殖だったり、少しずれているんですけどね。自分たちがやってることは少し変わっているので、他では真似されにくいと思います。」
牧場が起点となり、地域の中に循環を生み出したい

今後、ゆうぼくや岡崎さんが取り組んでいきたいことはあるのだろうか。
「やっぱり餌作りでしょうか。自給飼料にすごく興味があります。今、輸入に頼っている飼料コーンなどの高騰がすごいんです。金銭的なことだけでなく、輸入をするということは環境負荷も増えるので、できるだけ近場で循環できる仕組みをつくっていきたいです。先代から、地元の飼料米や稲わらを活用してというのは少しずつ実現できているので、トウモロコシなどにも取り組みたいですね。生産者のコミュニティができて、飼料を作り、堆肥は畑に戻すといった、経済的な循環とモノの循環が生み出せないかっていうのは、最近すごく意識するようになりましたね。」
世界中の広大な農地で一気に生産される飼料は、日本の小さな農地では規模も価格も対抗できないと言われてきた。しかし岡崎さんは、先代から脈々と続く、やっていないことを形にするスタイルをここでも発揮していきそうだ。最後に、岡崎さんは『食文化』という言葉をどう捉えますか?
「食べ物は、身体を作るのはもちろん、やっぱり心を育てるというところに絶対関わってくると思うんですよ。だからこそ、美味しいものを食べるときはすごく幸せな気持ちになるし、美味しいものを食べた後にはいい仕事ができるとかってあるじゃないですか。食文化っていうと、やっぱりその国々や地方にあって、ソウルフードのようなものですよね。例えば一時期北海道に住んでいた時、愛媛のものが出てきたらなんか懐かしいなって気持ちに溢れて。そういう意味で、食文化は、人々の心の支えになっているものなんじゃないかなと思いますね。」
ゆうぼくで生産された肉や加工品、そしてログハウスの中で食べる風景も、きっと地元の人たちの食文化になり、ほっとする瞬間を生み出すものになっているのだろう。
●取材を終えて
私は、兵庫県神戸市の農村地域で、個人事業として農村地域に関わる仕事を受け、小規模で農業をしている。そんな働き方なので、三越を舞台にして食の新しいあり方に挑戦するデザイン事務所の代表や、県内に数店舗を持ち、多岐に渡る戦略を繰り出す牧場の代表の話を聞くというのは、少し気が引けていた。しかしお話を伺うと、お二人とも、子どもの頃に触れた家族の稲作の風景や、数頭の牛から始まる風景が原体験となっていた。規模やインパクトだけを追い求めているのではなく、地方が、地域が、一つの食卓が、よりよいものになっていくにはという大前提があることに共感した。一方で、これは自分自身が痛感していることだが、地域の暮らしを維持していくためには、地域に残りたい、そしてこの場所に住んでみたいという若者の雇用の受け皿を作り、新しい仕組みを作っていく覚悟も持たないといけない。リスクを取りながら、こうして愛媛県で歩みを進めていくお二人の話を聞いて、自分の5年後10年後のあり方を考えさせられるようだった。

記事では書ききれなかったことなど、取材時の様子を動画で公開しています。
より詳しくご覧になりたい方はこちらから。
文:鶴巻耕介
写真:岩本順平