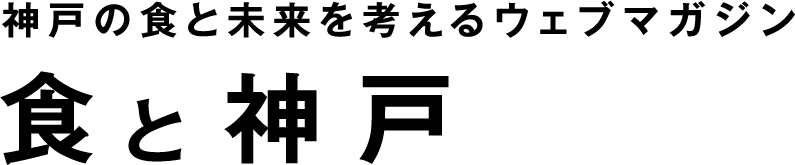瀬戸内の食文化をめぐるレポート vol.8 和歌山 後編(つくる)
瀬戸内各県で生まれ始めている、新たな食にまつわる活動や動きを展開している方々を訪ねていくレポート。今回は和歌山県の後編です。
(前編はこちら)
やっぱり自分は、漁師になりたかった

浜を背にすると、すぐに急峻な山があり、家々がそこに建ち並ぶ。日本のアマルフィとも呼ばれている雑賀崎という漁村で、ある漁師を訪ねた。
「生まれはこの雑賀崎で、漁師の一家です。船の手伝いや、魚も海も好きでしたが、継ぎたいとも継ぎたくないとも思ってなかったですね。物心ついたときから、漁師にならんでええと言われてきましたし。」
漁師というと、厳しい気候や激しい波と戦う漢というイメージだが、今回お話を伺った池田佳祐さんは、IT企業の社員ではないかという雰囲気や出で立ち。和歌山が好きで、県内で就職したつもりが、入社数か月で東京へ転勤。都会暮らしにしっくりこなかった池田さんは、実家の漁師という職業について、人知れず調べ始める。漁業を取り巻く課題を把握し、こうしたらいいんじゃないかという仮説も生まれてきた。そんなある年の末、父親にそれらのことを提案すると、池田さんは忘れられない一言をもらうことになる。
「『漁師なめてんのか!お前はもう陸(おか)に上がったんやから海のことは気にせんでいいわ。』って言われて。年末の酒の席だったもので、別のスイッチが入ってしまい(笑)でもそれがぐさって響いたんですよね。なんかもう海からえらい遠いところにいるんだと思って。そこからもっと勉強して、継ぎたいという話を1年後にしました。ちょうど30歳になる頃ですね。」
雑賀崎は、家族単位で船を持ち、ほとんどが小型底曳網(そこびきあみ)漁業を営んでいる。池田さんは、父親と船に乗ることで漁師の道を歩み出した。
価格決定権を持ち、漁師の強みを活かした新規事業を

池田さんは、漁師としての腕を磨きつつ、学んできた課題や仮説を行動に移していく。雑賀崎は、10年ほど前に仲買人が少なくなり、競りが出来なくなったことから、船から上がってきた魚をその場で販売する浜売りという手法を取ってきた。直売することは労力もかかりリスクもあるが、これが結果的に漁師の価格決定権を生んだ。自由に直売できるというメリットを活かし、池田さんは産直のネット販売なども試みている。そして、漁師という仕事の新たな打ち手として、池田さんが始めたのは『漁家民泊』だ。
「雑賀崎の漁師は、資源の保護や価格の低下を防ぐため、年間で100日ぐらいしか漁に出ないんですよ。もちろん船のメンテナンスもしていますが、休みが結構あるんですよね。当然お金になりません。そうした中で、漁家民泊という制度があるのを知りました。空き家も多いし、こうした町並みは海外の人も好きちゃうかなっていうのがあって、まずは一つ作ってみようと。」
池田さんは、クラウドファンディングで資金を集め、2021年7月に、曾祖父の屋号『新七』を引継ぎ、『新七屋(しんちや)』と名付けた宿泊施設をオープンした。築60年の古民家をリノベーションした空間で、雑賀崎に移り住んだような感覚が味わえる。
「私みたいにUターンして、空き家もあるしっていう人がいたら漁家民泊をやってほしいですし、そのモデルになりたいです。そうすれば、無理して魚が安い時に漁に出なくていいですし、うまいことバランスを取って漁師を続けていけるかなと。」
資源や環境とのバランス、そして漁師を続けていくための稼ぎとのバランス。池田さんは、今あるものを活用しながら、新しい漁師のあり方を模索している。

漁師のあり方を変え、自らの言葉で伝えていく世界を作りたい

今後、やっていきたいことはあるのだろうか。
「次にやりたいのは、漁業体験です。イタリアに妻と行ったときに、ぺスカツーリズムっていう考え方に触れました。体験して終わり、見て終わりではなくて、船長さんはなぜこうしたツーリズムをしているのかということからしっかりと語ります。魚を獲った後も、秘密の島みたいなところに降ろされて、ちょっと泳いでる間に、獲った魚を使ったランチがもう船の後ろに並んでいるんです。それをワインとか飲みながら食べて。めちゃくちゃ楽しかったんですよね。それぐらいのことをサービスとして提供できれば、商売としての可能性も含めて、日本でも漁業のあり方がガラッと変わるんじゃないかなと。」
こうやって話を聞いていると、池田さんは、これらのアイデアで自分だけが儲けようとしているのではなく、常に、後に続く世代ができる仕組みを作れないかと考えているようだ。実家に戻って漁師をやると決めたときに、漁を基軸としながらも、漁家民泊やツーリズムもあるという選択肢を見せていく。そういった別の楽しいと思える要素が、後継者を繋いでいく一手になるのかもしれない。最後に、池田さんは『食文化』という言葉をどう捉えますか?
「魚という生きている生き物を、海から取らせてもらっている感覚があります。まず、そうした生き物の扱いを大事にしないと、文化も何もそんなところではないなと思っています。例えば切り身の状態でも、こういう魚だったんだとか、この魚ってこんなに綺麗なんやとか、そういうことを伝える役割が漁師なのではと思っていて。食べた魚のタンパクというか、アミノ酸が分解されて体の一部になっていくといったこともですね。漁村の食文化という面でいくと、どうやって食べるのが美味しいとか、こういうふうに保存したらいいよとか、その辺りをちゃんと漁師がやったらもっと魚を食べる人が増えるはずです。競りに出したら楽やけど、食べて美味しかったよって言われんと。直接繋がることはやっぱり一番大事かなと思いますね。」
漁師がメッセンジャーになる。消費者もつながろうとする。そうした新しい関係性が、池田さんを中心に雑賀崎で生まれていっているような気がした。
●取材を終えて
「柔らかな方だなぁ。」今回和歌山の2件の取材で、大谷さんにも、池田さんにも感じたことだ。農村も漁村も、目の前にある課題はとてつもなく大きい。私自身も神戸の農村で地域に関する活動に関わっているが、課題を目にすると、「かつてのやり方はこうだからだめなんだ。だからこうするべきなんだ。」とすぐに対立を煽ってしまうような人がいたり、課題を単純化したりしてしまう人も多い。しかしお二人は、内なる課題感や信念は持ちつつも、こうした環境は、本来は面白くて、魅力的で、価値があるんだという前向きな捉え方で人を巻き込んでいる。みかんを収穫することも、魚を獲ることも、その地で食事をし、泊まることも、そうした場所に住んでいない人にとってはすべてが価値のあること。その接点を作り出し、お互いに頼っていく。そうした関係性の先に課題へのアプローチがある。そんなことを教えていただいたような気がした。
記事では書ききれなかったことなど、取材時の様子を動画で公開しています。
より詳しくご覧になりたい方はこちらから。
文:鶴巻耕介
写真:岩本順平