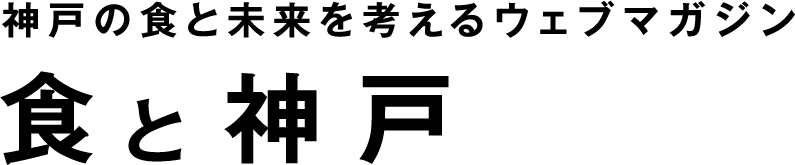瀬戸内の食文化をめぐるレポート vol.10 岡山 後編(ひろげる)
瀬戸内各県で生まれ始めている、新たな食にまつわる活動や動きを展開している方々を訪ねていくレポート。今回は岡山県の後編です。
(前編はこちら)
時期のもん、旬のもん。美味しい理由は、そこにあった

岡山市内から西へ1時間。広島県との県境にある笠岡市に向かう。瀬戸内海を眺めるその先には、笠岡諸島と呼ばれる島々を見ることができる。そんな港町にある、凛とした佇まいの日本料理屋を訪ねた。
「出身は、ここ笠岡の隣の里庄町というところです。海が本当に近いですので、小さい頃は釣りについて行ったり、アサリを採ったり。そういうところもあって、自然を食べるといいますか、そういった環境で育っていたのかもしれませんね。」
一言一言言葉を選んで話す姿は、まさに職人。5年前に、笠岡市で日本料理屋『美然』を開いた藤井宏行さんに、ひろげる人としてお話を伺う。藤井さんは、幼少期から食事作りの手伝いをするのが好きで、自然と料理の道を志すようになった。京都や岡山市内で料理の腕を磨き、35歳までには自分の店を持つという目標を叶えるために、どこで店を出すのか考え始めた。そんな時、自分の一番近くにヒントがあった。
「度々実家に帰ったりすると、うちの母親も結構料理が好きで、その時期のものをシンプルに料理するような感じでありまして。ふと、自分が仕事で作っているものより、家で食べる料理の方が美味しいなと感じたことがありました。聞いてみたら、『時期のもんだから、旬のもんだから。』と。それしか言わないんです。岡山市内でと思ったこともあったんですけれど、生まれ育った場所で店をやろうと決めました。」
魚も、野菜も、そして空気でさえもやはり肌に馴染むこの地元で、自分の店を開くために動き出した。
真の美味は自然の中に

藤井さんは30歳で地元に戻り、物件探しと並行しながらつくり手に出会っていく。
「地元と言えど、分からないことばかりでしたので、地元の漁師さんや魚屋さんと接し出して色々教えてもらいました。最初は中々手厳しく、何にも知らんだろうがという感じでしたが、しばらく通い続けると、そんなところの魚は駄目だ、これ食ってみいとかね。信頼関係といいますか、最近では本当にありがたく、いいものがあったら持ってきてくださるようになりました。」
そうした日々を積み重ね、実に5年の歳月をかけて、生き物を育てるように関係性をじっくり育みお店を構えていった。藤井さんは、身の回りにあるもので、そのときのもので料理を作ろうと決めた。漁師たちに聞きながら旬のものを仕入れ、地の人が作る新鮮な野菜や果物を教えてもらいながら分けてもらう。
「店の名である美然というのは、『真の美味は自然のなかに』という意味を込めています。本当に、自然の一番いい時期の美味しさというのは、もう感動するような美味しさがあります。調理では出せない、なんとも言えない感動に至る美味しさといいますか。自然のものの、その時のよさを皆さんに届けていきたいというのが一番ですね。」
私たち取材班は、この取材の後、実際にお料理をいただくことができた。感動に至る美味しさとはまさにこのことかと、藤井さんの言葉を思い返しながら箸を進めた。私たちが伺った時は、風の強い日が続き漁に出られない日々だったそうだが、季節の牡蠣や赤貝を中心に、まさにその時ある旬のもので、本当に幸せな時間を作っていただいた。


美然で感じたことを、日々の中に

今後、美然として取り組んでいきたいことはあるのだろうか。
「自然次第なところは本当にありまして、この先どうなっていくんだろうというのもあります。漁師さんたちも次の世代に繋げたり、魚を保護するための取り組みをされたりしています。私は、そういったことを、ここに食事に来られた方に料理を通じて知ってもらって、考えるきっかけになったらいいなと思っています。」
ここ笠岡でも、藤井さんが幼かったころにたくさん採れたアサリがほとんど採れないといったようなことが起こっている。埋め立てや気候の変化などにより、30年前から年々状況が変わっていることを肌で感じているという。そういった中、料理を作るものとして、藤井さんが捉える『食文化』とはどんなことだろうか。
「なんともこれは難しいです。色んなことが理由というのはあると思うんですけれど、今の家庭での食事というのは、やっぱり何か寂しいといいますか。時期の、旬のものは本当に栄養もありますし、その美味しさと感動とで心も体も育っていくものなんです。それは特別なことではなく、自然のことで、日々のことで、季節のことで。その毎日のことが連なれば文化って感じがするんですけども。自分が子どものときは、小魚とか、地の魚とかが多くて、その当時はやだなとは思ってましたけど、大人になってからはその記憶や感覚がありがたく感じます。今は蕗の薹が出てますけど、蕗の薹を食べたときに懐かしさを感じるような、そういったことがベースであってほしいですね。」
お店というその場所で料理を楽しんで終わりではなく、その体験を通して少しでも日常の食卓に変化が起こるように。そんな想いを持ちながら、藤井さんは今日も厨房に立ち、一皿一皿の背景をお客さんに語りかけていく。
●取材を終えて
今回は、美然で食事もいただき、ARCH FARM植田さんのパクチーもその場で分けていただくことができたので、2か所ともそこで作られているものを口にすることができた。語彙力に欠けて恐縮なのだが、ただただ美味いのである。植田さんのパクチーは、移動中の車内で一口味見をしたところ手が止まらなくなり、一束をそのまま根っこまで食べてしまった。美然でいただいた食事は、未だ口の中にあの時の美味しさが思い出されるようである。私自身都市部から神戸の農村に移住した人間であるが、そのきっかけとなったのは、社会に出た最初の赴任先が宮城県であったことだ。宮城県内の米、野菜、そして魚、素材そのものが美味しいという感覚に人生で初めて気付いたのがこの時であった。美味しさに説明は不要なのだ。「旬のもの、地のものを食べよう」とわざわざ説明が必要な時は、その圧倒的な感覚をまだ味わえていないのだ。まずはその入り口、きっかけを。農家という立場と、料理人という立場。やっていることは異なれど、食の原点を知るきっかけを淡々と作り続けるお二人の元を、色んな人に訪ねてほしいと思った。
記事では書ききれなかったことなど、取材時の様子を動画で公開しています。
より詳しくご覧になりたい方はこちらから。
文:鶴巻耕介
写真:岩本順平